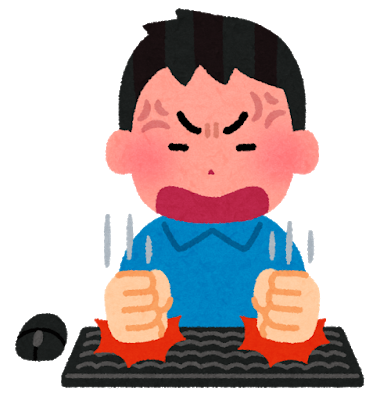作曲ができない!
できるようになりたいけど、どうしていいかわからない!
今回はそんな悩みについて、解決方法を書いていきます。
結論から言いましょう。
「”作曲ができない”は”勘違い”です」
ふざけんなー!!現にできないんじゃー!!
こんな怒りの声が聴こえてきそうですが…
順を追ってワケを説明していきますね。

僕は現在プロとして作曲・編曲の仕事をしています。
僕も作曲をはじめたての頃は
「作曲ってめちゃくちゃ難しい!自分はまだマトモに作曲なんてできないな…」
そう思っていました。
でもある時考え方を変えることにしたんです。
その結果、作曲することが精神的にとても楽になりました。
今回は僕がプロになるまでに培ってきた経験から、
あなたの「作曲ができないマインド」を解消していきたいと思います。
Contents
「作曲ができない」が勘違いなワケ

ワンフレーズでも立派な作曲である
そもそも作曲とはなんでしょうか?
さまざまな考え方がありますが、
僕は究極のところ「メロディを作ること」だと思います。
つまり鼻歌だろうがピアノで作ったワンフレーズだろうがそれは立派な「作曲」です。
詭弁だと思われるかもしれませんが、
この「ワンフレーズを作れるスキル」が完成品への大きな一歩なんです。
そのワンフレーズはとても大事な「タネ」になる
たかが鼻歌・ワンフレーズと侮ってはいけません。
作ったワンフレーズは完成品の「タネ」になるからです。
タネがあるか無いかで、作曲の初速が全然ちがってきます。
よく0から1を作る作業が一番大変と言われますが、
このタネをつくっている時点で0→1の作業が(ある程度)できているわけです。
実はプロの作曲家は、
ボイスメモで鼻歌を録りためておいたりモチーフだけのトラックを作っておく人が多い。
先輩の作曲家でレコード大賞をとっている方もこの習慣をもっています。
ボイスメモにネタを貯めておくことは、誰でもできて効果が高いテクニックです。
「作曲ができない」と思ってしまう理由
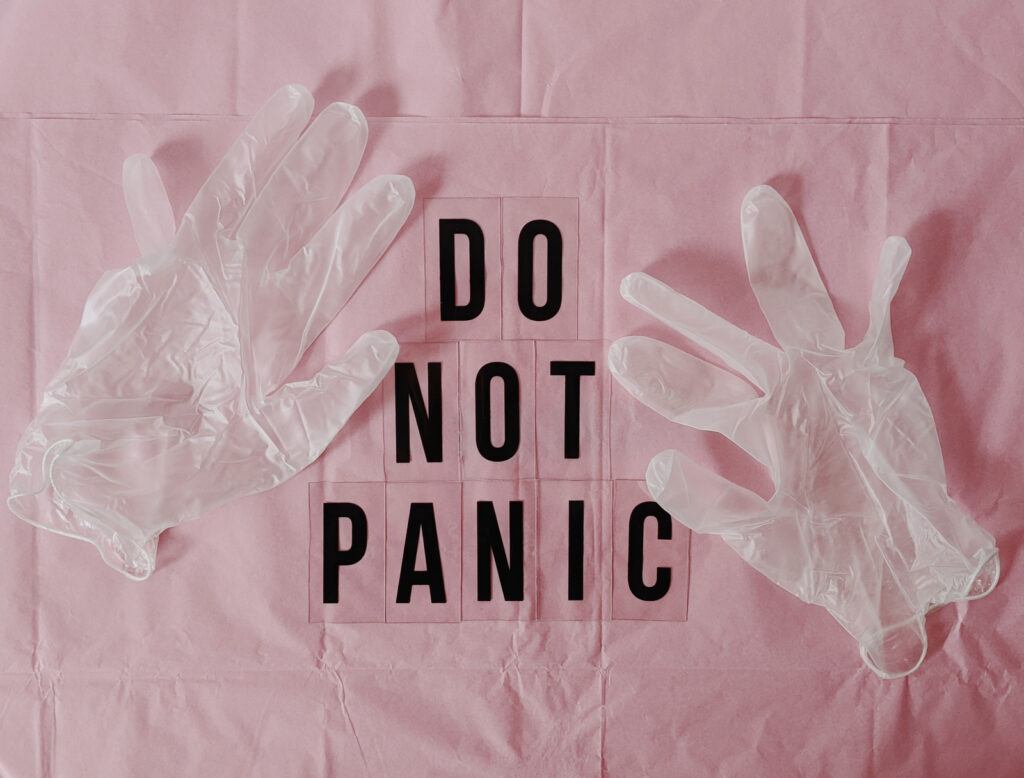
ではなぜ「作曲ができない」と思ってしまうのか。
理由は2つあると思います。
- メロディに合うコードが見つからない
- みんながつまづくのは大抵「編曲」である
一つづつ見ていきましょう。
①メロディに合うコードが見つからない

最大の理由はコレなのではないでしょうか?
いいメロディを思いついた。
でもこの後どうすればいいのかわからない。
もしくはコードをつけようと思ってもなぜかしっくりこない。
この場合の解決方法は
- そのメロディの「キーとスケール」を知ること
- 「コードの知識」を知ること
- 「コードの型」を知ること
の3つです。
個別に説明するとどうしても長くなってしまうので、詳細は別記事にまとめたいと思います。
概要だけ説明していきますね。
まず、メロディが先にあって作曲を進めていくやり方は
キー・スケールを判別する → コードをつけていく
という手順をふみます。
つまり、まずは「キー」「スケール」「コード」という言葉を理解する必要があります。
「キー」と「コード」は聞いたことがある人が多いのではないでしょうか?
ただ詳しい意味を聞かれると困ってしまうかもしれません。
学術的に言うと、
- キーとは、
「スケールの主音を示したもの」 - スケールとは、
「ある雰囲気をもった音のつらなり」 - コードとは、
「和音・ハーモニーのこと」
です。
この説明ではっきり理解できた人はすごい。
僕は最初に聞いたとき「な、何をいってるんだこいつは…」と思ったものです(笑)。
最初はこういう学術的な説明は覚えなくて大丈夫です。
ひとまず覚えてほしいのは、
メロディを曲に仕上げるためには、キー・スケール・コードの知識が必要
大変ですが、ひとつづつクリアしていけば必ずたどり着けます。
②みんながつまづくのは大抵「編曲」である

僕は作曲と編曲(アレンジ)を切りわけて考えることが大切だと考えています。
「編曲」という言葉は聞いたことがあるけど意味はわからん、という方が多いのではないでしょうか?
編曲はざっくり言うと「曲に楽器をつけていく作業」です。
なぜ作曲と編曲を分けて考えるべきかと言うと、必要な知識や技術が違うから。
編曲には楽器や音楽ジャンルの知識、そして演奏技術が必要なのです。
僕が初心者のころ、作曲と編曲を切り分けて考えたことですごくスッキリと作業できた記憶があります。
ひとまず、
「メロディとコードができれば作曲は完成!」
「編曲には別なスキルが必要なんだ!」
と考えてみましょう。
「作曲ができない」状態から、リリースされているような「完成品」をつくるには?

ではアーティストの楽器のような「完成品」をつくるにはどうすればいいのでしょうか?
方法は2つあります。
- 編曲を覚える
- 他の人に編曲してもらう
編曲を覚える

完成品をつくるには編曲作業が必須です。
一人でやるなら、こればっかりは勉強して覚えるしかありません。
現代ではDTM(デスクトップミュージック=コンピュータで音楽を作っていく方法)が主流。
特にDAW(作曲ソフト)の操作をおぼえるのは大抵の人にとって苦痛になるので、
わかりやすい本や動画、スクールを調べておくとよいと思います。
他の人に編曲してもらう


しかし一人でやらないのであれば話は別です。
特にバンドメンバーがいる場合は、
各メンバーに編曲を任せることをオススメします。
その方が速く・質も高くなりますし、
バンドメンバーの「オリジナリティ」を発揮できる場所を作ってあげられますしね。
バンドメンバーはいない…でも編曲するのは大変だし、作曲に専念したい!
こんな場合は外注するのも手です。
今は個人やクラウドソーシングで仕事をしているアレンジャー(編曲をする人)も多いですから、
探して編曲をお願いするわけです。
この方法のメリットは、
- 完成までの時間短縮
- クオリティがあがる
- 編曲を覚える手間をはぶける
が挙がります。なかなか大きいですよね。
もちろんデメリットもあります。
- お金がかかる
- かかる費用もクオリティもアレンジャーによってマチマチ
- 自分の好みにあうアレンジャーを探すのが大変
特にたくさんリリースしたい時は費用がかさんで大変…。
でも一度パートナーが見つかれば、曲作りが段違いにスムーズになります。
「編曲をまったく覚えなくていい」わけではない
イェ~イ!これで編曲を勉強しないで済むぞ!
と思った方は要注意。
編曲の知識が全くないとアレンジャーとやりとりするときにめちゃくちゃ不便です。
例えば修正依頼をするとき、
「なんかイメージと違うから修正をお願いしたいけど、なんて言ったらいいのかわからない…」
という状態になってしまいます。
僕はアレンジャーとして参加したコライト(共作)作業で、
この状態の作曲家さんとやりとりしたことがありますがハッキリ言って地獄でした。
何が悪いのかわからないけどコレじゃない感があるんだよねぇ…
という反応のくりかえし。
こっちは良いと思って作っているわけですから、
具体的にどこが良くないのかわからないと改善のしようがないですよね。
そしてこの作曲家さんの言動を聞いて、かなり失礼な印象を受けたのではないでしょうか?
でもこの時本人は無意識でした。
(言葉はきついですが)無知ゆえに失礼かどうかの判断もできなかったわけです。
こんな時にある程度編曲の知識があれば、
「ギターのカッティングが入っていた方がよりファンキーになって好みです」
「ドラムがロックすぎる感じがするので、もう少しタイトなビートにしたいです」
など具体的な注文をつけることができ、
より少ないやりとりで、ストレスなく理想のイメージに近づけられます。
アレンジャーと良好な関係を築くためにも、
最低限の知識は頭に入れておきましょう!
「作曲ができない」状態からマインドチェンジしよう


ながながと書いてきましたが、ここで大事なことをまとめたいと思います。
ワンフレーズをつくることから始めよう
ワンフレーズでも立派な作曲です。
ボイスメモにとりためておく事で大事な「タネ」が増えていきます。
マインドを変える = 作曲を「すごいことだと考えない」
作曲は誰でもできます。
「完成品をつくらなきゃ作曲じゃない!」という考えは『悪い完璧主義』。
もっとラクに、楽しんで作曲していきましょう。
作曲するためにまず必要な知識
作曲をスムーズにするために必要な知識は、
- キーとスケール
- コード
の2つです。
まずはこの2つの知識を重点的に勉強してみましょう。
まとめ:脱「作曲ができない」


今回は「作曲ができない」状態からぬけだすための方法をまとめてみました。
作曲をするのは思っているよりも簡単です。
ただ、「名曲をつくる」のは至難の技であることは間違いありません。
僕もまだまだ勉強中なので、一緒にがんばっていきましょうね!
それでは!